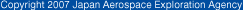宇宙連詩 第2期
「星があるの巻」
ぼくのなかには星がある
ずっとむかしのことを思ったりすると
からだじゅうがむずむずしてくる
きっとぼくに入る前のことがなつかしくなって
星がピョンピョンはしゃいでいるにちがいない
星のなかでは水がゆれている
その水は ともしびをかかげていた
ともしびは にんげんたちの しんぞうだった
軍服の肩に飾られる星 国旗にずらりと並ぶ星
レストランの格付けに駆り出される星
失神する主人公の頭上に飛び散る漫画の星
天上の星と違って地上の星たちは忙しい
ときにエトワールの座を競いあって
星印 というと頭に浮かぶあの記号
実際の星のかたちとは似ても似つかない
でも「星の砂」を可愛いと感じるのは あの記号のおかげなのだ たぶん
銀河より海、海より川
川より古里の池の中の星光は
私に一番近いなじみのある光
どんなに離れても、どんなに暗い日々に陥っても
その光は照らしてくれる
私のたどる一條の光
一歩ごとに 次の一歩から何光年
私は本当にふさわしいのか この旅に
地球の中で眠っていた一粒の鉱石に
はるか彼方から一筋の光がさしこむ
過去の石と未来の光がとけあい
命をえたようにあざやかな色が輝く
一瞬の輝きに永遠をかいま見る
太陽はひっかき、力を光子にしてふるい落とす
黄金の塵として、すべての惑星に向けて。ただひとつ地球だけは
どろどろの黄金の夢を育み、わが永遠の分け前として、太陽に投げ返す。
私は生まれた日の朝、この旅を始めた。
空の深みに生まれた星が私の守護天使。
おのれの光によって私の体と魂、私のすべての夢を見守る。
夜明け―星は窓辺に鳩を送る。空の家への帰り道の
空気の記号の読み解き方を、私に教えるために。
果しなく 広がっている 空間に
微塵となって 飛び回っている
夢かうつつか 星屑 みたいなわたし
闇があるからこそ星屑は金属の粒のように光る
漆黒を背にした金銀の砂絵のように
光は燃え盛る力、闇は真空のエネルギー
二つのバランスの中をすべてが飛び交って伝わる
尾を引く私の心も彗星のように巡り来る
ほんの少しの岩石のかけらよ、群れ集まり、凍りつき、無私無欲に押し込める
あらあらしいスピードで、あんなにも容赦なく、あんなにもすばやく、漆黒を背に
究極の寒さ、その魔法のような真空を、いったいどこからあなたの願いは来るのか。
瞬きの時間も惜しんで願いをかけた8月
ペルセウスの方角に瞳を凝らし、君の心臓の鼓動を感じながら
もうすぐ会えるよ、と話しかけた
産声は50億年を旅してやっと届いた光
息子よ、君はそうやって地球(ここ)に来たんだよ
地球(ここ)も星の上だということを思い出せたら
もう少し優しくなれたかもしれない
おそろしく不機嫌だった今朝の私
きらめくのはあなたの涙か、それとも希望ですか、
この宇宙の広大な広がりのなかで? 静脈のように脈打っている
私たち自身の宇宙のなかで。地球から送られてくる
さまざまな信号を観察している。ひょっとしたら
私たちの信号をも。
ぼくたちのあふれる想いは
今や世界中をとびかっている
でんぱという、小さな小さな感動をぎょうしゅくした波となって
凝縮したエネルギーが勢いをつけて飛散する
空間と時間の中へ破片をまき散らしながら。
さながら隕石の群れのように
それとも花咲いた桜の木立ちを吹く微風のように
費やされたエネルギーの互いにばらばらな反響となって...
青空の向こうにも星が出ているなんて いったい誰が言ったんだろう
鸚鵡石が力強く応える 「見えないものも 確かにそこにある」と
それが「自然」なんだと
君が太陽であるならば
私は月であろう
君がすべてを照らすなら
私はその光を受けて
君の内にある 闇を照らそう
毎晩 星が私のまつげに触れる
光は私のまゆから出ずる
私の魂のドアをノックしながら
スイッチを押すとつく 電気の明かり
ホッとする明るさ 暖かい光
難しいことは よくわからない
ただ 電気を 暖かい と感じるのは
人間が昔から 太陽や 月や 星を 知っていたからだろう
見よ、文明の驚くべき影を。
人間たちは花を摘み、花束を縁どり、愛する者に贈る、
そして告げる、自分の愛がいつまでも無傷なままで永遠に新鮮であるだろうと。
ずっと輝き続けるかのように見える星たちは
いつの日か消えてしまうのかもしれない
それでも
その輝きに馳せる私の思いは きっと永遠にあり続けるのだろう
いくつもの、誰かの思いと連なりながら
だから最後に 星くずに照らされた道
そこを夢は立ち去るのだ 燠火のようなメッセージを
朝の私たちの 眼の底の灰に残して