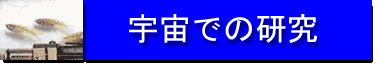
第27回宇宙ステーション利用計画ワークショップ開催結果報告 第2日目
1日目に続き2日目は、初期利用に続く「きぼう」日本実験棟利用の新たな展開についてそれぞれの分野から報告がありました。
 第1日目 第1日目  開催案内 開催案内
 第2日目(〜初期利用に続くきぼう利用の新たな展開〜) 第2日目(〜初期利用に続くきぼう利用の新たな展開〜)
 |
JAXA宇宙環境利用センター長
田中哲夫 |
JAXA宇宙環境利用センターの田中哲夫センター長から、「きぼう」の初期利用、そしてそれに続く2次利用のスケジュールや方針について報告がありました。また、利用に向けて準備をしている実験装置などが紹介されました。今後の方針として、来年度には、これまでの検討や議論を具体的な案として取りまとめて提案し、本格的に推進を始める必要があることを報告しました。
 きぼう利用の重点化のあり方 きぼう利用の重点化のあり方
 |
大同工業大学学長
澤岡昭 |
大同工業大学の澤岡昭学長は、「きぼう」、及びISS利用の重要性、利用領域の重点化、今抱えている課題にについて報告しました。「きぼう」、及びISS利用の重要性では、科学技術の歴史上において、とても重要であることを説明し、第2期利用に向けて最大の効果が得られるよう、関心ある研究者、技術者は勿論のこと、利用について多くの人々の積極的な発言が必要であると報告しました。
 各分野のきぼう利用ビジョンと戦略 各分野のきぼう利用ビジョンと戦略
1) 宇宙環境利用科学研究
 |
JAXA宇宙科学研究本部教授
栗林一彦 |
JAXA宇宙科学研究本部の栗林一彦教授は、初期利用に向けた生命科学分野と物質科学分野の実験の準備状況、及びそれぞれの実験の目的について報告しました。
また、初期利用に続く2次利用と永続的な利用に、宇宙環境の科学的利用の一元的な推進体制の必要性を説明しました。現在、物質科学、生命科学及び基礎科学の各分野において、研究者の自由な発想に基づく研究班ワーキンググループの提案を募り、それを支援することにより研究者コミュニティの育成を図っていることを報告しました。
2) 有人宇宙技術開発/宇宙医学
 |
JAXA有人宇宙技術部部長
柳川孝二 |
JAXA有人宇宙技術部の柳川孝二部長は、初期利用に続く「きぼう」利用の新たな展開として、有人宇宙技術と宇宙医学の開発に望んでいく展望を報告しました。有人宇宙技術に関しては、現行の宇宙服が抱える様々な課題を解決し、日本製の宇宙服を開発する展望を説明し、宇宙医学の展望については軌道上での治療など、宇宙医学の高度化の必要性について説明をしました。
3) 曝露部利用
〜宇宙・地球研究〜
 |
JAXA宇宙科学研究本部教授
小杉健朗 |
JAXA宇宙科学研究本部の小杉健朗教授は、「きぼう」の船外実験プラットフォームを利用した科学観測についての考え方などを説明し、科学観測において、宇宙科学分野、地球科学分野に重点を置いて進めていることを報告しました。初期利用で行う観測やその装置について説明があり、第2期に向けて検討中のプログラムが紹介されました。
〜技術開発〜
 |
JAXA執行役
渡辺篤太郎 |
JAXA執行役の渡辺篤太郎氏は、宇宙実験・実証の必要性や重要性、その目的や手段などについて報告を行いました。宇宙実験・実証の例なども紹介され、「きぼう」を利用して効率的、効果的に実験・実証が実施できるように準備を進めていることが紹介され、「きぼう」の特徴を活かした利用法を拡張するための構想が紹介されました。
4) 応用利用
 |
JAXA参事
加納剛 |
JAXA参事である加納剛氏からは、応用利用分野において機能材料の自己組織化による創製、微小重力空間での比重の異なる要素からなる機能性複合構造の創製などを重点的に推進していると報告しました。また、宇宙で生成した物質の産業利用の可能性について報告しました。
5) 教育をはじめとする一般利用
 |
多摩六都科学館館長
高柳雄一 |
多摩六都科学館の高柳雄一館長は、「きぼう」の一般利用分野についてその意義と目標、現在かかえている課題やその対策について報告しました。また、教育・文化的活動として野口聡一宇宙飛行士が軌道上で撮影したビデオメッセージを紹介し、一般利用分野の役割は、宇宙利用を科学者や宇宙飛行士だけではなく、一般の人々へ向けることであると、一般利用分野の展望を報告しました。
 宇宙環境利用への新たな挑戦 〜落下塔からスペースシップワンまで〜 宇宙環境利用への新たな挑戦 〜落下塔からスペースシップワンまで〜
 |
NPO法人北海道宇宙科学技術創成センター専務理事
伊藤献一 |
NPO法人北海道宇宙科学技術創成センター(HATIC)の伊藤献一専務理事は、HASTICが提供しているハイブリッドロケットや微小重力実験が行える落下塔などを紹介しました。また、昨年のスペースシップワンのサブオービタル飛行が米国で成功した事例を紹介し、サブオービタル飛行の国内導入の検討を進めていることを報告しました。これが実現すれば国内で約3分間の無重力が体験でき、宇宙旅行者の国内支援や、微小重力実験の支援につながることを説明しました。
 宇宙映像ビジネス 〜SPACE Films〜 宇宙映像ビジネス 〜SPACE Films〜
 |
(株)スペースフィルムズ
高松聡 |
(株)スペースフィルムズ代表取締役社長の高松聡氏は、自身が作成を担当した日清食品株式会社のカップヌードルのCM作成までの経緯について報告しました。今後は宇宙からの映像を広告に利用することができ、広告として提供することにより、ISSを知らない人々にも、ISSからの映像を見てもらうことにより、ISSを知ってもらえる機会が増えることを説明しました。そして、今回の撮影をきっかけに宇宙の映像を提供する基盤を作ることに成功したことを報告しました。
(4) 初期利用に続くきぼう利用について -パネルディスカッション- |
各分野からの代表をパネリストに迎え、"初期利用に続く「きぼう」利用について"をテーマに「きぼう」初期利用の後、より実りある成果を目指して、意向の利用フェーズにおける利用の重点をどこに置いていくべきか、そして、「きぼう」初期利用の後、どんな利用の未来を切り開けるのかについて活発な議論が行われました。
 |
 |
 |
司会進行役を務めた大同工業大学学長
澤岡昭 |
パネリスト |
 第27回宇宙ステーション利用計画ワークショップ閉会式 第27回宇宙ステーション利用計画ワークショップ閉会式
 |
JAXA顧問
井口洋夫 |
JAXA顧問の井口洋夫氏は、このような国際的なプトジェクトは今後、国際共同研究する際のいい経験となり、いい事例となると述べました。そして最後に、間近になった「きぼう」の具体的な利用に向けて、貴重な意見を実現に向けて努力が必要であることを述べ、第27回宇宙ステーション利用計画ワークショップは閉会しました。
 会場の様子 会場の様子
2日間を通して、パネル展示や成果報告書、パンフレットなどが配布されました。
 |
 |
 |
 |
| 多目的実験ラックのシミュレーションコーナ |
植物栽培実験装置の紹介 |
実験や無重量環境を利用して撮影された映像の紹介 |
研究成果のパネル展示 |
 |
 |
| 会場となった江戸東京博物館大ホール |
最終更新日:2005年12月22日
|
